有限会社キャニッツのサイトへようこそ。
- このページはログとして残っている古いページです。
- リンク切れや、現状にそぐわない記述などが含まれる場合が御座います。
- また過去の技術で作られたページもあり、きちんと表示されない場合も御座います。
どうぞご了承頂いた上でご覧ください
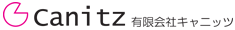
・また怪談のひみつ
登場人物紹介

博士 ・ 蟹太くん ・ 通子ちゃん ・ 怪談番長
博士 :何でも知ってる偉い人。
今回は博士の青年期の話だよ。
蟹太くん :好奇心旺盛な少年。わりと頭が悪い。
今回は蟹太くんの回想という設定だよ。
通子ちゃん:蟹太くんの友だち。割と性格が悪い。
今回は出番があんまりないよ。
怪談番長 :怪談番長。
今回は彼が主役級の扱いだ。
正月だから怪談をしよう
私が小学生だった頃、近所に一人の老人が住んでいた。彼は、
額が――あくまで額だと、彼は言い張っていた――頭頂を過ぎて
後頭部にまで後退し、いつもくたびれた白衣と指紋の付いた眼鏡
を身につけ、髪の色と同じ真っ白な口ひげをたくわえていた。年
のころは、今にして思えば七十か八十はいっていたと思えるが、
当時小学生だった私は彼の年齢などよくわからなかった。子ども
にとって老人は老人、大人は大人、それ外の何者でもない。
彼の住まいの中には子どもの興味を引きそうながらくたや、埃
にまみれた古い書物などが雑然と詰め込まれ、彼は一日中部屋に
閉じこもって思索に耽るか、書き物をするか、得体の知れない器
具を使って何らかの作業をしているかだった。
彼は子どもの目にはどこをどうとっても博士に見えたし、彼自
身も博士を自称していたので、私と通子――当時の女友達――は
偶然に彼の知己を得、それ以来彼の家に入り浸るようになってか
らも、彼の本名を知らずにただ博士と呼んでいた。
ある年の正月、三日あたりだと思うが、私と通子は連れだって
博士の家へ遊びに出かけた。表向きは年始の挨拶ということにな
っていたが、何のことはない、お年玉をせびりに行っただけのこ
とだった。その日こそが、私が忘れようと願っても忘れえぬ日、
これまでの生涯に幾度となく悪夢に現れ、これからも悩まされ続
けるであろう日なのだった。
始まりはこんな感じだったはずだ。
「――博士、あの夏のときの怪談、あれ嘘なのでしょう?」
と、通子が言った。夏の怪談とは、その前年の八月のあたま頃、
博士が話してくれた怪談だった。彼の少年時代の思い出の形式を
とってはいたが、それが真実なのかどうかは判断がしかねた。
「さあ、どうかな。なにしろ昔の話だ」
私は博士のからかうような口調に多少の苛立ちを覚え、彼に詰
め寄ったのだと思う。
「博士、自分では面白い冗談なのだと思ってるかもしれないけど、
こっちとしては本当のことが知りたいだけなんだから、あんまり
ごまかさないで教えてよ」
「うん、――本当のことと言うがね、真実とはそんな簡単なもの
じゃあないんだよ」
「そして真実は人の数だけあるとか、また使い古された文句を言
って逃げようとするんだ。本当か嘘かわからないから面白いんだ
とか思ってるんだろうけど、そんなことは全然ないよ」
「いや、真実とは人の数だけあるのではなく、そんなものは最初
から無いのだとわしは思うのだ。これは年を重ねれば気づくかも
しれないし、一生わからないかもしれない。――でも、こういう
形而上の話はまだ面白くないだろうし、よし、では別の話をして
あげよう。
――今度は、わしの青年時代の話だ」
そして、博士はまた別の怪談を語りはじめたのだった。
回想の話の中の回想の話
わしがあらゆる類の知識を知識のそれゆえに愛し、何らの専攻
分野を持たないことは前にも話したし、君たちにもよく承知のこ
とと思う。終戦してしばらくの事だった。わしは一向に目のでな
い学究の徒で、自分には学才があると言い聞かせながら、二流の
大学で不定期に講師をして食い扶持をつないでいた。
そのときは地政学の分野での論文を学会に認めさせようとやっ
きになっていたが、研究のためにも発表のためにも費用はかかる
し、何はなくとも生活費がかかる。親類縁者のつてを頼って借金
をして回っていた。妻にはずいぶん苦労させた。
そうだ通子ちゃん、妻がいたんだ。見合いで結婚したのだが、
わしは彼女を愛していたし、彼女も文句一つ言わずにわしのため
に尽くしてくれた。色が白くて、額の綺麗な娘だった。若かった
わしは、臆面もなく彼女の綺麗な額が好きだなどと言ったものだ。
彼女は照れた素振りも見せずに、――あなたのおでこも素敵です
よと、言い返したものだ。
おっと蟹太くんそう笑うものでもない。わしだって若い時分に
は緑なす黒髪がこうふさふさと、――いや、それはどうでもいい。
とにかく、赤貧ではあったが、わしら若い夫婦はとてもうまくや
っていたのだよ。あるときわしが彼女に麝香の匂い袋を贈ったこ
とがあったが、彼女はそれをとても大事にしてくれた。
だが、彼女は生来病弱だったのだ。五年ほど連れ添ったところ
で、倒れた。風邪をこじらせて肺炎にかかってしまったんだな。
ろくな暖房も衣類もなく冬を越させてしまったのだから当然とも
言える。わしは研究を中断し、彼女の看病にあたった。医者に見
せる金などありはしなかったので、ほぼつきっきりでいたとは言
え、彼女は徐々に衰弱していった。
彼女の看病に専念してから一年ほどだ。ある朝、彼女が薄い布
団の中で言ったのだ。
「――わたし、もう長くないと思います」
もちろんわしは否定したさ。彼女は長い闘病が生来の白さに拍
車をかけ、ほんとうに真っ白な顔色をしていた。わしは彼女の額
に手をかけ、――そんなことはない、と言ったものだ。
「ご自分の天命だと言っておられた学問を、わたしのために投げ
出して、あなたもさぞかしつらかったと思うのです。――今日ま
で手厚く見ていただいて、わたし、ほんとうに感謝しています。
でも、自分でわかるのです。わたし、今日のうちに――」
一年ずっと看病していたのだから、わしもわかった。それで、
彼女にはそのまま言わせておこうと思ったのだ。彼女がいつも持
っていてくれた麝香の匂い袋の香りが、そのときもしていた。
「ただ、ひとつだけ、お願いがあります。――あなた、これから
一人になって、それで、さみしいだろうと思うのです。――でも、
どうか、私の後に妻を娶らないでほしいのです。こんなことを言
うのは嫉妬が深いとお思いでしょうが、それでもわたし、あなた
がほかのひとと一緒になるのだと考えると、耐えきれなくて――。
お願い、できますか」
わしはそのとき泣いていたのだと思う。彼女の額に手を当て、
彼女の目をのぞき込みながら――、
「――わかった。妻は取らない。取るものか」
そう約束した。
そして、その日の夕暮れ過ぎ、太陽を追いかけるようにして、
彼女は逝ってしまった。
わしは彼女のために墓を作る金が無かった。田舎から東京に移
した先祖の墓も空襲で跡形もなく、手製の仏壇に位牌があるだけ。
近所の住職の好意で経だけはしてもらったが、葬式代もなかった。
火葬もできん。彼女の身体はわしの家の狭い庭に埋め、石屋にも
らった石を置いて墓標にした。彼女の大事にしていた麝香の匂い
袋も彼女と一緒に埋めた。
それからわしは学究の生活に戻った。一年が過ぎたころ、親類
や友人からしきりに再婚を勧められた。――子をなさなければ、
誰が先祖の供養をするのだ、彼女とて君がいなくなれば無縁にな
り、手を合わせるものもおらんだろう――。とね。
もう喪は明けたのだし、なくなられた細君も君が幸せになるの
を望んでいるはずだ――。と。
わしは一人で暮らすことに疲れていたのだな。わしの家に染み
ついていた麝香の臭いが消えるころ、わしは大学の知人の紹介で
新しい妻をもらった。その娘も色が白く、額の美しい娘だった。
わしはその顔に彼女の面影を見るのが嫌で、家を空けがちにして
大学の研究室で過ごすことが多くなった。
ある朝、わしが大学に泊まり込んで帰ると、新しい妻の態度が
おかしいのに気づいた。わしは自分の勝手のせいで妻にかまって
やれないので気を悪くしているのだと思った。
「家にあまり居着かないですまない。だが、男の仕事というもの
はそう簡単なものではないんだ」
などと言って宥めようとした。だが、妻は不満はありませんと
言うばかりだった。そして、その日の夜もわしは研究室に泊まり
込んで家には帰らなかった。
次の日に帰宅すると、妻はますます様子がおかしく、顔色も優
れないようだった。わしは尋ねた。
「どこか具合でも悪いのか。まるで病人のような顔だ」
「いえ。それが――」
そういったきり妻は黙りこくってしまった。わしは問いただし
た。
「なにか問題があるなら言ってもらいたい。君に何かあっては親
御さんに申し訳が立たないし、君を紹介してくれた人にだって、
わしは何と詫びたらいいのか」
「はい。――それが、お庭の石のことですけど。あれは、前の奥
様のお墓だとか――」
「ああ墓だ。元の妻の墓だ。――墓のすぐそばで暮らすのは、厭
なのか」
「いえ。こんなものは気の迷いだとおっしゃるかもしれませんが、
わたし、前の奥様の声が、寝ているとき聞こえるんです」
「声――。声が。それは、何と言っているのかね――」
「別れろと。――あの人と別れてくださいと。この家を、すぐに
出ていって欲しいと」
わしは腕を組んだ。妻は庭の石が彼女の墓であると知り、わし
が彼女の思い出を捨てきれないのを知り、それが夢に出てしまっ
たのかもしれない。そのとき、わしは葛藤と夢の関係についても
勉強をしていたところだった。
「おそらくそれは夢で、君がわしの後妻になっていることへの、
何か後ろめたい気持ちが表れた事だと思う――」
「夢でしょうか。きのうも、おとついも、縁側の障子のそとに、
女の人の影が映るように思えるんです。夢でしょうか。そして、
声と臭いが――」
「臭い――」
「ええ。麝香の臭いが」
「麝香の――」
その晩、わしは妻を安心させるため、寝室で不寝の番をするこ
とにした。わしがいる夜は彼女が現れないというので、寝室の隅
についたてを立て、その影で夜を明かすことにした。
さて、その晩が更けた。深夜の二時を回っても、なにも起こら
なかった。わしは、起こるはずのないことは起きぬという確信と、
奇妙な期待感とのないまぜになった、内蔵を圧迫するような気分
に陥っていた。そんな気分で夜を過ごすと喉が渇くものだ。わし
は妻の寝顔の白い額を確認してから、台所の汲み置き水を飲みに
行った。
そして、寝室に帰ってくるとき――
声が聞こえた。
「――出て行けと言ったのに――」
それは低い女の声で、彼女の声に似ているように思えた。
「――別れろと言ったのに。あの人と一緒になるなと言ったのに。
ああ、その白いおでこを、あの人は好いてくださるのか――」
わしは寝室のふすま越しに動けないでいた。誰が動けようか。
だが――
「――その、白いおでこが、憎い――」
妻の悲鳴が聞こえるのを合図に、わしの体は動いた。ふすまを
開け、寝室へ入ると――
寝室は血だらけで、妻は仰向けに倒れていた。妻の顔は、額か
ら顎にかけて、皮膚と肉とが削ぎ取られていた。
部屋は麝香の臭いがした。
回想の中の回想の話が終わり
博士の話は終わった。
「――それじゃあ、あんまりだ。彼女が恨むべきは博士であって、
新しい奥さんじゃないはずだ」
私は言った。だが、通子は別の意見があるようだった。
「いいえ、そうじゃないと思うわ。だって――」
「男にはわからないとでも言うのかい。女なら女の方を恨むと、
わかるとでもいうのかい」
「そうじゃなくて。
――なぜ、彼女は博士に復讐しなかったと思うの」
そして、それは通子の言うとおりだった。
そのとき、博士が自分の顔に手をあげていったのだが、それは
眼鏡の位置を正すいつもの癖のためではなかった。
これ以上、私には続ける勇気がない。
|
このページのTopへ戻る
蟹通トップページへ
|
Copyright 2000-2008 Canitz co.,ltd. All Right Reserved.

